最近、ランニング中に道端でタヌキに遭遇しました。
めっちゃかわいかったですよ。
それと一昨日、昨日と予備試験の論文試験でした。
当日の記憶が鮮明なうちに各科目の感想を残しておきます。
各科目の感想
憲法
(1)青少年が図書Aを購入できないこと、(2)成人が年齢確認を受けなければ図書Bを購入できないことという、2つの異なる制約事由について憲法21条適合性について問われる問題で、比較の視点が問われていたと思います。
ただ、答案書いてる最中に迷いが生じて(2)の制約事由に関する手段審査が不十分な結果となりました。一応最後まで書いて「以上」で終わりましたがそこが残念。
迷いが生じた理由としては、それぞれの制約される自由につき知る自由で構成したんですが、図書を出版する側の自由として構成することも問われてるのかな、と思って迷いが生じて筆が遅くなったんですね。結局時間的に処理するのは無理と判断して書かなかったんですが、当初検討した構成についても時間的に書ききることができませんでした。
成績予想としては、どうでしょう。
知る自由構成も間違えとは思えないし、問題文の事情に突っ込んで比較の視点も意識しました。
他方、(2)の手段審査の検討が不十分でそこは点数が入ってこないだろうし、憲法21条1項はライバルもカチッと書いてくることが予想されます。
だから、EかFてとこですかね。ただ、底Fはないと思います。
行政法
行政法は原告適格と本案違法性が問われました。
これはわりかし書けましたね。簡単だったと思います。
成績予想としては、AかBですかね。
刑法
刑法は簡単な問題だったと思います。
時間的にも余裕があったので丁寧に処理したんですが、甘かったです。
一つ論点書ききれず途中答案となりました。。
ただ、答案の完成度としては90%近くできあがってて、書いた内容自体は、わりと本文事情をうまく評価して処理したんで個人的にはいい感じに思います。この場合の途中答案てどうなんですかね。
成績予想としてはC~Eて感じですかね。刑法はレッドオーシャンだそうで、途中答案が悔やまれます。
刑訴
刑訴は訴因変更の同一性の可否と黙示的択一的認定がでました。
訴因変更の同一性の可否はうまく処理できました。おそらくこっちはA、悪くてB評価。
問題は黙示的択一的認定です。
こっちは、「疑わしきは被告人の利益に」の原則(利益原則)から規範をつくって処理しました。
だから規範とあてはめの部分は正解筋だと思います。
ただ、適用条文を335条として、「罪となるべき事実」の問題として処理してしまいました。
「罪となるべき事実」の定義→本件では~。→利益原則→規範定立→あてはめ、ていうちょっと訳わからん構成になりました。
択一的認定の問題となる条文(336条)を理解してなかったですね。択一式認定の対策が手薄になってて理解が不十分だったのが原因です。
成績予想としては、B~Cてとこですかね。
一応、利益原則からの処理とあてはめという箇所に部分点が入ってくるだろう、他の受験生も黙示的択一の対策が手薄になっていただろう、という希望的意味合いを込めてます。
租税法
租税法は、問題文が多かったですね。
時間切れにならないよう、さくさくっと処理しました。
問題が6こあったんですが、最後は時間切れで解ききれませんでしたね。
ただ、条文を使って処理したし問題文の事情を使って評価も示せたし、一応の答案を完成できてよかったです。
成績予想としては、C~Eてとこですかね。
民事実務基礎
これ、結構な分量でした。しかも素直な問題でなく少しクセのある問題。
まともに解いたら沈没するなと思い、あらかじめ決めていた時間を過ぎて損切して刑事実務基礎にいきました。
これが正解でした。
11問中1問まともに解ききれませんでしたが、最終的には納得できる答案の形に仕上げることができました。準備書面も1ページちょっと書き上げることができました。
この実務基礎の時間中、「おそらくここで一定程度の受験生は沈没する、ここで負けなければ合格可能性が高まる」と思い、結果的に負けなかったので、これに関しては自分を褒めたいですね。
成績予想としては、B-Dてとこですかね。
刑事実務基礎
こっちは、民事実務基礎がやばい印象だったのでさくさくっと解くことを目標にしていました。
結果、スピード重視で1時間13分で解き終えました。
出来としては、そんなとんちんかんなことを書いてる印象はないですね。
試験後、刑事実務基礎の答案回収の際、他の受験生の答案も見えたんですが、表面だけで終わってる受験生がちらほらいました。多分時間切れになったんだと思います。
成績予想としては、他の受験生の出来がそこまでだろうということを加味してA~Cてとこですかね。
民実、刑実あわせた成績としては、B~CでワンチャンAてとこですかね。
民法
これは曲者でした。
短答プロパー知識が必要になる問題がでましたし、分量も多かったです。
条文を使って端的に処理しましたが、時間なかったんで5問中1問解けませんでした。
成績予想としては、E~Fてとこですかね。底Fはないかと思います。
商法
これ、設問1(2)の問題で、会社法339条2項類推適用の構成で処理したんですが、正しくは会社と取締役の任用契約違反の問題が出題趣旨だと思います。外しました。
他方、他に2問でたんですが、そこはしっかり処理できました。
成績予想としては、C~Dてとこですかね。
民訴
まさかの、220条4号二の処理問題がでてきました。
これは多くの受験生にとって想定外だったと思います。
私は、若干判例とは違った規範を立ててしまいました。
あてはめで問題文の事実を評価したのはよかったと思います。
もう一つの問題は、一部請求に対する反訴に対する原告の相殺の抗弁の問題でした。
一応、一部請求の趣旨から論理立てて構成して外側説で着地しました。問題ないかなと思います。
成績予想としては、A~Bですかね。
総括
ミスや力不足による失点はあるもののこれも実力です。ただ、とんでもない失点はないかと思います。
おそらく各科目、底Fはないですね。
行政法,、民訴が自信あって、実務基礎はワンチャンA、刑法、刑訴は採点者の心象で成績が振れる気がします。
まぁ、これは成績相場観のない一受験生の見解なんで分かりません。
ひとつ、よかった点としては、最後まで諦めなかったことですね。
実務基礎と民事系のうち民事実務と民法の問題で「マジかよ」て思ったんですが、冷静に、他の受験生が沈没するだろうからここが勝負所だと思って、自分なりに得点の最大化を目指す方向で処理できたことについて、自分を褒めたいです。
試験が終了した頃はヘロヘロになってました。
それと短答試験後から論文試験までの7週間、論パタ復習、典型論点確認、要件事実(大島本)、予備過去問添削、辰巳模試に取り組んだんですが、実力が大幅にアップした気がします。
合否は全く予想できないですが、どちらの可能性もあることを想定して動いていきます。
しばらく、10月中旬くらいまでは予備試験の勉強から離れます。
お疲れ様でした。
それでは。



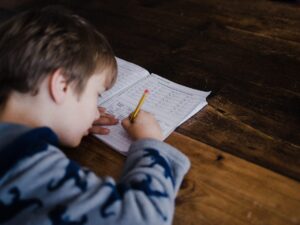
コメント